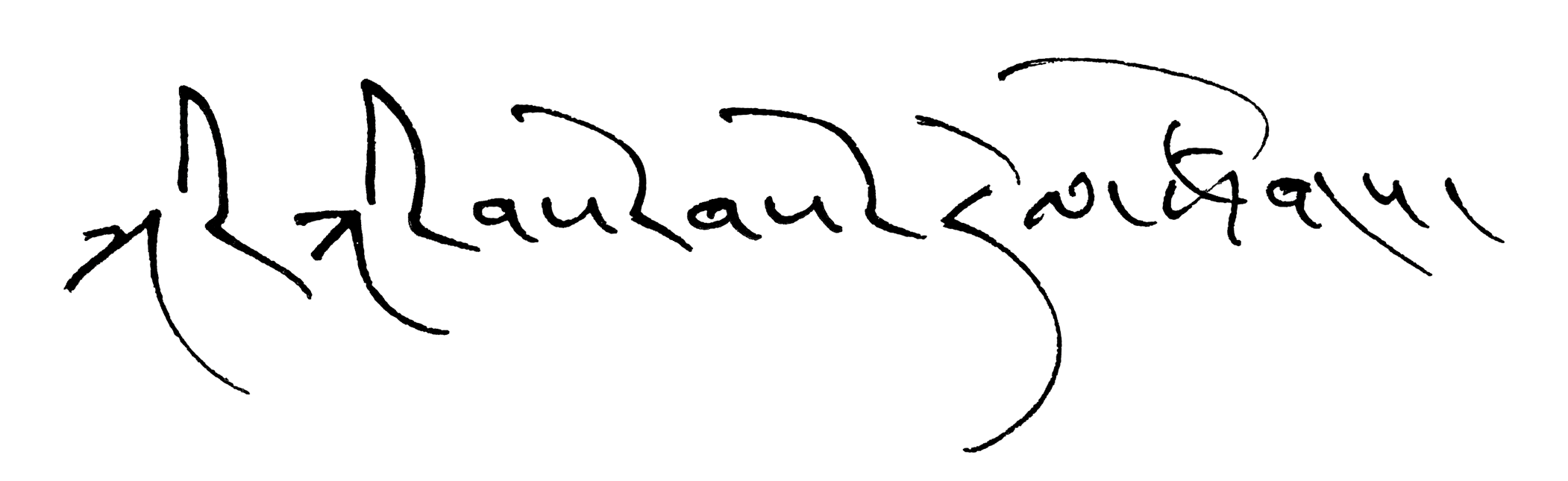2023/09/12 00:00

2018年秋、長野県小諸市。チベットの文化や心を伝えたいと2015年から開催されている「キキソソチベットまつり」。終始和やかな空気が流れていたおまつりのエンディング、主宰者の在日チベット人ゲニェン・テンジンは人々の輪の中で声を震わせていた。
「ここでは当たり前に自由に歌ったり踊ったり、おまつりをすることができるけど、チベットでは人がたくさん集まると何かを企んでいるとされるので、簡単ではない。」
光もあてられず苦しむ故郷の人々のことを言葉にしようとすると嗚咽となった。
ゲニェンはチベットで生まれ、幼少期にインドへ亡命したチベット難民の一人だ。彼のこれまでの道程を辿った。
私は1980年代初め、チベット自治区内の農村で生まれた。兄弟は9人で、家族で主食であるツァンパ(裸麦)や野菜を栽培し、牛や馬、羊、山羊などを飼っていた。私はおしゃべりで人が好きな子供だった。私は兄弟の中で記憶力が良かったらしく、6歳ごろから僧侶の長兄のいる仏教僧院へ預けられ、お経を習い始めた。後に僧侶になるための準備期間だった。自分でも僧侶になりたいと言っていた。チベットでは家からより多く僧侶を出すことが良いこととされていて、私の家でも3人の兄が僧侶になっていた。
家から離れての修行生活は厳しく退屈だったので、私はなんとか遊ぶことや逃げ出すことばかり考えていたようだ。次兄によると私はベッドの下におもちゃを沢山隠していて、兄が「勉強もしないで遊んでばかりいるな」と叱ると、お経はしっかりと暗誦してみせたという。ある日はお供えに使う神聖な場所の湧水を汲みに行くと言って小さな瓶を持って出て一日中戻らなかったりした。
幼い私にはチベットがどういう状況だったかはわからないし、大人も教えない。けれど、僧侶の兄がビラの代筆をしたというだけで数ヶ月投獄されたりしていた。1980年代後半、僧侶による大規模な抗議行動が起こっていた時代だった。
数年した頃、それまでとても厳しく何も買ってくれなかった長兄がラサの街へ私を連れて行き、服や靴、サングラスなどを買ってくれた。それぞれ二つずつあった。旅行に行くんだよと言われ、楽しみになった。兄が急に優しくなったのはなぜだろうと思いながら。
ある朝、いつも一緒にお寺の学校に登校している友達が私を迎えに来たが、長兄が「ゲニェンは今日は具合が悪いから学校へは行かないよ」と言ったのが不思議で、どこも悪くないのにと思った。その夜、大きなトラックがやってきて、暗がりの中私はそのトラックの荷台に乗せられた。中に入ってみると荷台は人でいっぱいだった。それは国外への亡命者を運ぶ車だった。当初、長兄は私を連れてインドへ一緒に亡命する計画だったが、一家の長でもあった長兄はチベットに残ることになり、兄の親友である僧侶に私を託すことになった。亡命する十数人の同行者と共に、両親にも兄弟にも知らせぬまま、私は故郷を離れた。両親に話せば猛反対されるとの長兄の判断だった。当時よりチベット内での教育は中国への迎合を強いるもので、1990年代初め頃には子供たちの将来を危ぶんだ親たちが、チベット人としての教育を受けさせるため多くの子供をインドへ送っていた。チベット人の最大の心の拠り所であるダライ・ラマ法王のいるインドなら、我が子を安心して託せるというのが多くの親が思っていることだった。私はそれが家族と故郷との長い別れとも知らず、旅行の始まりにワクワクしていた。
車で数日移動した後、そこからは徒歩の旅だった。ヒマラヤの雪道を2週間ほど歩いた。監視に見つからないように昼間寝て夜歩く。ある時は起きると顔に雪が降り積もっていたりした。苛酷な道程にチベットへ引き返す人や、命を落としてしまう人もいる。しかし旅行と思い込まされ、故郷を離れる悲壮感もない幼い呑気な私は道中歌を歌ったりして、体調も崩さず歩き通すことができた。長兄が買ってくれた二つのサングラスは雪の反射光から目を守ってくれた。一つ落としても大丈夫なように二つ。靴が破れてももう一足。凍傷を防ぐための手袋。必要なものをすべて下調べしての準備だった。
チベットを抜け、辿り着いた先はネパール・カトマンドゥの難民移送センター。そこで出された最初の食事で、長兄に私を託された僧侶が気を遣って、食べ慣れないネパールのダール(豆スープ)は口に合わないだろうと「この子はあまり食べないよ」と言うのをよそに3杯も食べてしまった。あまりに美味しかったのだ。ダールはその後入学するインドのチベット人寄宿学校で12年間、嫌という程食べることになる。
つづく
ゲニェン・テンジン
聞き書き / 柳田祥子

チベット自治区ラサのジョカン寺前で兄と