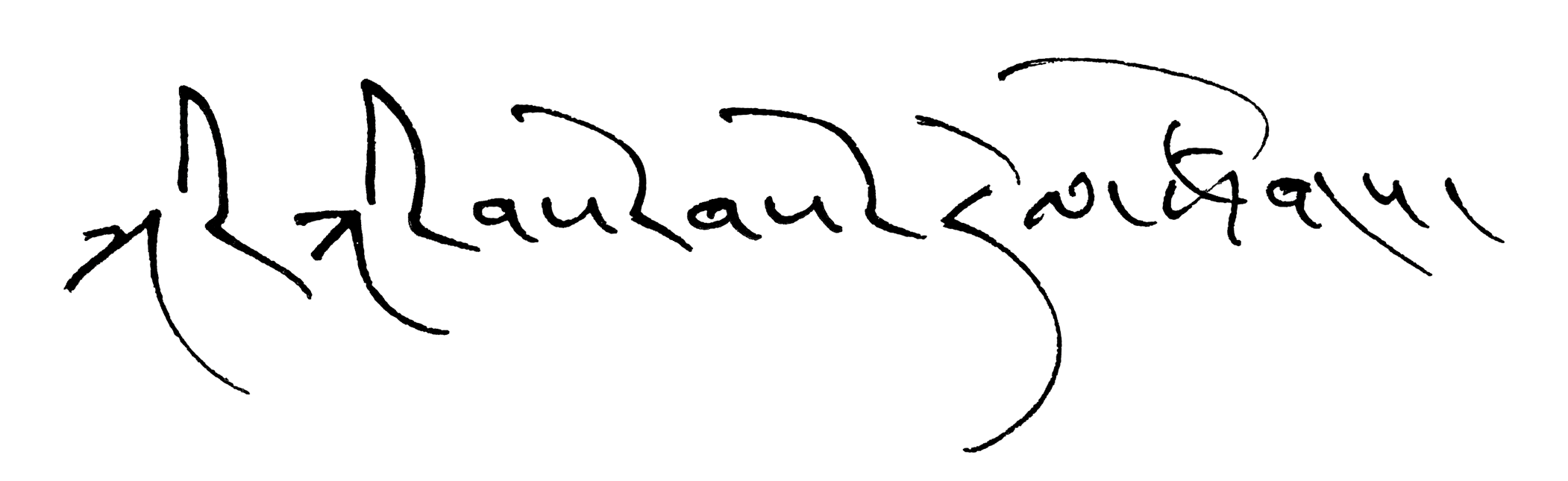2023/09/28 14:00
カイラス山の標高5000mを超える巡礼路で一番元気なのは私だった。チベットに着いてから私はずっと興奮していて、高山病になる暇もなかった。久々の故郷の味はどれもとびきり美味しく、何を見てもとにかく触ったり口に入れたりしたかった。道端の土さえも汚いと思えず、舐めてみたりする私に同行者は驚いていたが、24年ぶりに触れる故郷のエネルギーを少しでも取り入れたかったのだろう。
私は巡礼路で数歩歩いては立ち止まって苦しそうにしていた中国人の女性の手を引き、最高到達地点まで一緒に登った。その女性にチベット人かと尋ねられたので、「日本人です」と答えた。
中国やチベットでは昔から日本人を悪者に描いたプロパガンダ映画をやっていたので、少しでも日本のイメージが良くなるといいなと思った。こんな高地でピンピンしている屈強な日本人がいるのかと思われたかもしれないが...。巡礼で見た山々はどこか悲しそうに、ダライ・ラマ法王と人々の帰還を待ち望むように、必死に何かを訴えかけてくるようだった。
巡礼を終え、ラサへ戻る途中には無数のチェックポストがあった。チェックポストに遭遇する度に車内には緊張が走り、ガイドも運転手も事なきを得ようと神経を使いながら警察官と言葉を交わす。黒い制服を着た警察官はチベット人だった。きつい仕事は中国人ではなくチベット人にやらせるのだ。警察官は銃を携え、側には消火器と先が輪になった長い棒が用意されていた。それは多発する焼身抗議に備えたものだ。
炎を消し止め、焼け焦げた遺体を素早く隠すために。回収された遺体は家族の元に戻されることはない。
そんな光景に様々な感情が重なり、私は車内でどうにも泣けてきて、しばらく嗚咽した。チベットに降り積もる人々の悲しみが、私の体を使って泣いたのかもしれない。
2日間かけてラサへと着いた日、私は残り数日となった旅の時間を惜しみ、一人でポタラ宮の周りを散策に出かけた。ホテルから近い距離を出歩く程度なら何も問題はなかった。ポタラ宮は歴代のダライ・ラマ法王が座す宮殿だが、現14世が1959年にインドに亡命して以来、ずっと主人の帰りを待ちわびている。
丘の上にそびえ立つ13階建ての荘厳な建築物はラサのシンボルで、チベット人なら知らない者はいないが、私が幼い頃の記憶を辿りながら散策していると、方向音痴も手伝って道に迷ってしまい、道端で商売をしているチベット人の女性に「ポタラ宮はどこですか?」とチベット語で尋ねた。どこからどう見てもチベット人の私にポタラ宮の場所を尋ねられた女性は私を驚いたように見つめたまま無言で、道は教えてもらえなかった。 よほどおかしな奴と思われたようだ。
その晩、父と兄弟全員、叔父が集まり、私達は24年ぶりに再会した。兄の一人が、私が来ていることは話さず「とにかく来い」と全員を呼び出し、普段はラサに行きたがらない叔父もなんとか説得して連れてきた。
集まった場所には私がいて、皆が驚きと再会の喜びに涙した。すべてが夢の中の出来事のようだった。
父は私に会えたから「もう死んでも悔いはない」と言った。私をインドに亡命させた長兄は、母が他界し、私に会わせられなかったことをずっと後悔していた。
私と父が再会できて心底安堵した様子で、大きな肩の荷が下りたと震えるように言葉を絞り出した。
長兄は多くは語らないが、自分の判断で私を亡命させたことを色々と考えてきたのだろう。私を含め皆が、長い年月の隙間をどう埋めていいのか、様々な感情が織り混ざっ た気持ちを表現する術を知らなかった。
数時間を楽しく過ごし、別れ際に私はやっと少し本音を出すことができた。 「私は帰らない!」と言って泣き、その場を走り回ったのだ。 小さな駄々っ子のように。それにつられて皆も泣いていた。
本当になぜ、私だけが帰らなければいけないのだろう。またいつ会えるかわからないという想いがさらに別れを辛くさせていた。
つづく